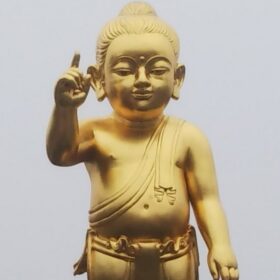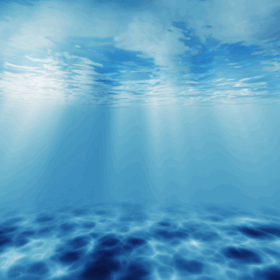1.自分らしくいきるために、気遣いの重荷を手放す方法
何故疲れるのか?
何となくしんどいと感じるとき、それは周りに気を遣い過ぎて無理をしているサインかもしれません。自分の思いや感覚を抑え続けると、気づいたときには疲弊しています。
本来、自分の思いをはっきり実感し、良いタイミングで伝えられれば、ストレスフリーな人生を送れるはずです。しかし多くの場合、幼少期から自分を抑えることが習慣になっていると、「無意識に人に合わせること」が自分の感覚だと勘違いしてしまいます。
本当の自分の感覚とは?
自分の感覚とは「無意識」に感じるものです。
・「好き・嫌い」の直感
・「ワクワクする」感覚
・「心地よい・心地悪い」の感覚
・「居心地が良い・悪い」と感じる瞬間などです。
これらの感覚は、他者からの評価よりもはるかに重要です。しかし、長年自分を抑えてきた人は、この「ワクワク」や「心地よさ」を感じにくくなっています。
自分の感覚を取り戻す第一歩
まずは「不快な感覚」に正直になることから始めていきます。
1.「行きたくない」と感じるお誘いは、勇気を持ってお断りする
2.時間的な都合より、気持ちの都合を優先する
3.「悪いな」という罪悪感は、親から刷り込まれたものなのでスルーしてOK(笑)
断るのは最初は勇気がいりますが、大人になった今、交友関係は「選んでもいい」のです。自分に合った関係性を知り、合わない関係には距離を置いてみます。
その結果「寂しさ」を感じることもありますが、それはもともと自分の中にあった感情です。その寂しさと向き合い、手放していくことが大切なポイントです。
気遣いを手放すために
気遣いを手放すには、過去のネガティブな感情を手放す必要があります。気を遣い過ぎる習慣には理由があります。それは幼少期の体験から自分を守るために身につけたものです。当時は周りに合わせる方が生きやすかったのかもしれませんが、大人になった今、その習慣がしんどさを生み出しています。
こうした感情を日々少しずつ手放すための効果的な方法として、自分でも行える「セドナ・メソッド」という方法をご紹介いたします。これは創始者レスターレヴィンソン氏が提唱した、不快な感情をその場で手放し、本来の自分の能力を取り戻す方法です。
(私自身は、トラウマの影響が大きくありましたので、トラウマの解消をダイレクトに行う必要がありましたが、その前にこの方法でかなり感情が解放され楽になりましたのでご紹介いたします)
2.感情を手放す簡単な方法「セドナメソッド」
感情を手放すことは、実は想像以上に簡単なプロセスです。特に幼少期の体験から生まれたネガティブな感情を解放することで、より自由で軽やかな心を取り戻せます。
なぜ感情は手放せるのか
感情には実体がありません。何かのきっかけ(相手の言動や態度など)で生じますが、それはあくまで「きっかけ」であり、実際に反応しているのは自分の内側です。自分自身が反応して生じる感覚なので、自分で解消することができるのです。
しかし、多くの場合、私たちはこの仕組みに気づかず、感情に振り回され続けます。その結果、感情はモンスター化し「相手や環境が変わらなければ解決しない」という錯覚に陥ってしまいます。
感情を手放す簡単さを実感するエクササイズ
まずは、感情を手放すことがいかに簡単かを体感してみましょう
- ペンやボールペンなど握れるものを用意します
- そのものを強く握ってみてください
- 次に、そのものを離してみてください
離そうと思えば簡単に離せますし、握り続けることも自分の選択です。感情を手放すという行為も、これと同じくらいシンプルなのです。
セドナメソッドの具体的な手順
リラックスした状態で、目は開けても閉じてもかまいません。
1. 感情を認識する
気になる場面を思い浮かべ、その場面での感情を感じます。漠然と「嫌な感情」とひとくくりにせず、「不安」「焦り」「悲しみ」「寂しさ」「孤独」「怒り」など、具体的な感情を特定します。
2. 感情を認める
自分に問いかけます:「この○○(特定した感情)を認めることはできますか?」 この質問に「はい」か「いいえ」で答えます。「いいえ」でも問題ありません。自分に質問することで、選択肢が自分にあることを認識していきます。
3. 手放せるか尋ねる
「この○○の感情を手放せますか?」 ここでも「はい」「いいえ」どちらの答えでも大丈夫です。「いいえ」の場合は「今はそうなんだな」と受け入れ、別の機会に再度試みればよいのです。
4. 手放す決断をする
「はい」の場合、次の質問に進みます:「この○○の感情を手放しますか?」 これを3回繰り返し問いかけることで、手放すという決断を確固たるものにします。
5. 手放すタイミングを決める
「いつ手放しますか?」と自分に尋ね、直感的に答えを感じ取ります。「今」「明日」「来週」など。「今」と感じたら、すでに手放せている状態ですので、その解放された感覚を味わいましょう。
6. 身体感覚に注目する(応用編)
慣れてきたら、感情と共に現れる身体の反応(肩の張り、胸の圧迫感、頭の重さなど)に注目しながら上記のステップを行うと、さらに効果的です。
継続することの大切さ
「こんなことで手放せるはずがない」と判断してしまうと、ネガティブな感情を握りしめたままになってしまいます。感情を手放すことは簡単だという認識を持ち、毎日淡々と続けることが大切です。いつの日か「あ、手放せた」と感じる瞬間が必ず訪れます。
感情の解放は一度で完璧にできるものではありません。日常生活の中で感情が生じたときに、このシンプルな問いかけを繰り返し行い、徐々に手放す力を身につけていきましょう。
3.「心地よい」選択をして生きてみる
ネガティブな感情を手放せるようになると、感情に振り回されることが少なくなり、自分の本当の気持ちに正直に生きられるようになります。この状態なら「心地よさ」を基準に選択していく生き方が可能になります。
「嫌だ」と感じることを大切にする
感情に翻弄されなくなると素直に「嫌だな」と感じることができ、気遣いなく断れるようになります。この時大切なのは「迷惑」という概念を忘れず、相手の立場にたってお断りしたいですよね。
・物理的な迷惑(例:人数把握が必要な予約がある場合は、早くお断りする)と、感情的な気遣い(罪悪感など)を区別し気遣い(罪悪感など)は手放す
・お断りする際は、感謝と丁寧な言葉遣いを忘れない
・「嫌な感覚」は自分を守るためのサインとして大切にする
心地よさを優先することへの誤解
「自分の心地よさを優先すると我がままになる」という考えは、大きな誤解だと思います。
なぜなら、実際には:
・自分に優しく、自分を愛し大切にできる人は、心が穏やかで他者にも自然と優しくなる
・自己犠牲による貢献は長続きせず、内側に不満やストレスを蓄積させる
・本当の自分を大切にできる人ほど、他者も尊重し大切にできるからです
本質的な自分の声を聴く
自分を愛し大切にすると、徐々に「魂」や「本質的な自分」の望む方向性が見えてきます。
ここでいう「魂」は宗教的なものではなく、親や周囲の期待に合わせる前の本来の純粋な自分のことです。
私たちの多くは、成長過程で集団生活や社会適応のために「本当の気持ち」より「求められる行動」を優先することを学んできたため、本質的な自分の声を感じ取れなくなりました。
しかし、ネガティブな感情を手放し、自分を大切にする実践を重ねることで、本質的な自分の声を再び聴けるようになっていきます。
「本質的な自分」の声を聴くことは、これまで培った社会性を捨てることではなく、社会の中で自分本来の感覚を尊重しながら生きるバランスを見つけることです。これにより、外部からの期待に振り回されるのではなく、内側からの導きに従って進む自由を得られるのです。
:最後にネガティブな感情をなかなか手放せない場合もあり、それには理由があります。それは、幼少期のトラウマが深く根付いている可能性があるからです。 セドナ・メソッドを試みても、なお次のような状態が続く場合は、より深いレベルでの解放が必要なのかもしれません。
・同じパターンの感情が繰り返し現れる
・理屈では分かっていても感情が変わらない
・体の緊張や不快感が続く
FAP療法は、そんな深いトラウマが原因の症状にアプローチする方法です。FAP療法(不安からの解放プログラム)は、簡易的な催眠とセラピストとの脳の共感理解を応用し、言葉では表現できない感覚を解放していきます。